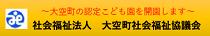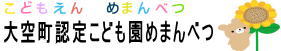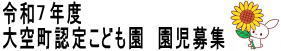園だより令和5年度第10号が発行されました
アーカイブ
園だよりR5【第9号】令和5年度前期 園評価
令和5年度前期の保護者と職員による評価結果の公表です。
園だよりR5【第8号】
園だより令和5年度第8号が発行されました
第2回園内研修会(10月17日)~ナナメの関係を大切に~
10月17日,第2回園内研修会を実施しました。
オホーツク教育局義務教育指導班生田裕章氏に指導助言をお願いし,滝上・東藻琴・訓子府の先生方を交えて保育公開と研究協議を行いました。
午前中は各クラスの保育公開を行い,子どもたちが集中して遊びに取り組んでいる姿を観ていただきました。
午後からは今日の保育の反省,協議のテーマである「さまざまな環境構成(遊具や製作物)と関わる園児の動きや保育教諭の支援のあり方」についてグループに分かれて話し合いを行いました。
園児が遊んでいる様子について活発な意見交換がされました。
遊戯室ではさまざまな遊具が用意されて,園児は興味関心のあるものを選んで遊んでいました。マットを引いて相撲をしたり,開園記念日で餅まきが楽しかったことを思い出して餅まきごっこをしました。
本園では,子どもたちがやってみたいと思うことを再現する経験を積み重ねたり,子どもの取組を認め,ほめることで自分には能力があることを認めるように手助けをしています。






本園で意図的に取り組んでいることは“異年齢交流”です。町内の小中学生が園児らと交流する機会があります。今年は9月に中学生が保育実習や職場体験で来園しました。
12月には小学生と園児が相互に行き来し交流する予定でいます。
生徒さんたちは,園児が夢中で遊んでくれそうな手づくりの遊具を持参してくれて園児たちは少し緊張しながらも楽しく遊んでいました。このような関係を「ナナメの関係」といいます。




お友だち同士は「ヨコの関係」,保護者と本人,先生と本人の関係は「タテの関係」,その真ん中あたりが「ナナメの関係」にあたります。
異年齢交流は少し特殊な関係ですが生徒(児童)と園児の双方にとってウインウインの関係をつくりだします。
園内でも同じような関係づくりを大切にしています。年長さんは下の子の面倒をみてやりがいや思いやりを感じる,下の子は「あんなふうになりたい」と年長さんにあこがれる。
先生が教えなくても子どもたちの潜在的な能力を引き出す取り組みを幾度となく積み重ねています。
園で身につけた力を就学しても活かすことができる,こんな力が身についているから一層伸ばしてほしいことを引き継ぐことがこども園と小学校の真の連携に繋がっていくように考えます。
園だよりR5【第7号】
園だより令和5年度第7号が発行されました
令和6年度大空町認定こども園保育教諭(新卒・正職員)再募集
採用予定人数に達しなかったため、令和6年度大空町認定こども園保育教諭(新卒・正職員)の再募集します。
(申 込)必要書類を大空町社会福祉協議会へ郵送ください。
(試験日)募集があり次第、随時おこないます。
※試験日程は書類選考後、個別にご連絡させていただきます。
園だよりR5【第6号】
園だより令和5年度第6号が発行されました
管内こども園実技研修会
8月1日,オホーツク管内3園(訓子府・東藻琴・女満別)の保育教諭が集まり,めまんべつこども園で実技研修会が行われました。
昨年はコロナ感染拡大のために中止になりましたが,今年はコロナが明けて開催することができました。
実技研の内容は,製作活動(ものづくり)でした。保育指導において製作活動は,園児にとってたくさんの効果があるとされています。
いくつか挙げてみると,
①作る楽しさがある。②集中力が高まる。③動作が身につく(はさみで切る・糊をぬる等)。④達成感が味わえる。
⑤季節や文化を感じられる等です。本園でも鯉のぼりや七夕など季節ごとにそれぞれの保育室や正面玄関前に園児の作品が飾られます。
こども園で扱う材料は,下の画像のように身近な材料(紙コップ,牛乳パック,セロテープ,紙テープ,ナイロンボールetc.)であることがポイントです。
理由は「間違えても,何度も作り直せる」「何個も作れる」「いろいろ違う形に挑戦できる」ということから,園児の満足感を充たしてくれる材料がたくさんあります。
これが製作キッドだとそうはいきません。一度失敗すると元には戻らない材料が多いので・・・・・。




製作活動は,そのねらいが<作ること>にあるのか,<使うこと>にあるのかで,こどもの頑張る場面や満足感は違ってきます。
製作したものは全体で交流,実際にどう使うのか試してみました。自分がイメージした通りに使うことができるのか検証することも大切です。
午後からは日常の保育や実践について情報交流を行いました。
交流の時間では,同じ悩みが共有できたり,新しいアイデアが発見できたり,明日からの保育指導に活かせる情報がたくさんありました。







園だよりR5【第5号】
令和5年度園だより第5号が発行されました。
第2回園内委員会を行いました。
7月18日,硯教育相談員と女満別小学校田村教諭に出席いただき2回目の園内委員会を行いました。
初めに1学期の前半のまとめとして各学級の園児のようすについて紙面交流を行いました。
4ヶ月が経過し少しずつできることが増えてきました。
①言葉が増えてきている,②排泄が確立した,③帽子をかぶる・かばんを持つ,④自分の部屋に戻れる,
⑤給食を頑張って食べる,⑥人と関わろうとする,⑦いろいろな物に興味を持つ。
このような情景は明日の保育指導や園児との接し方を前向きにしてくれます。
後半は3つのグループに分かれてケース協議を行いました。ある園児の生活のようすをもとにその困り感を把握して,どのような支援の方法があるか協議しました。
①身支度は,見通しをもたせた声かけを行う,②対人関係においては,園児の今の感情を動画に残して,それを見て振り返らせるといった具体的な手立ても出てきました。
保育教諭が1つのケースについて知恵を出し合い,「その子」に対する共通の言葉をもつことは組織的に対応していく上でとても大切です。
協議が進む中で,ふと気づいたことがありました。子どもは人にほめられても,自己承認欲求が満たされないと満足できないこと,その日がいい一日で終わらないこと,です。
人は誰から一番認められたいのか? 一番に認めて欲しい人はだれなのか・・・・
それは「自分」であること。自分から認められないと強い欲求不満状態になり,別の何かで解決しようとしてしまいます。
これは大人の世界にも当てはまります。「別の何か」という解決方法が悲惨なケースになることもあります。
話を進めていくうちに,何を目標に,どのような力を育んでいくのか,簡単ではないことに気付かされます。
「自分で自分のことをほめてあげる」,「自分は価値ある存在であることに気づかせる」,安心と信頼による関係づくり,子どもが意欲的に遊ぶ環境づくり,
真剣に話を聞くといった取り組みが効果的であることを確認しました。