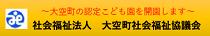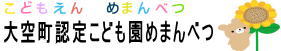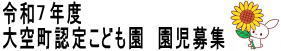今日のお花はサイネリアてす。「喜び」「快活」「明朗」という花言葉。誕生会には最適の花言葉。
たった一つの命を大切にしましょう。出し物は年少。みんなで寸劇をしました。
お誕生のお友達も、フロアの子どもたちも、お互いの命を大切にし合いました。
未満児一歳児「もも」組さんです。身のまわりの人や物にとっても関心が高まり、自分もやってみたいという好奇心が出てくる時期です。自分の衣服も自分で脱いだりできます。生活習慣が身についていく時期です。でも、まだ大人の手を必要とします。保育教諭の言った言葉の意味を理解できることが多くなります。
まもなく満二歳になります。二足歩行ができるようになってから、人間の大脳の前頭葉の働きがすごく早いです。
スキャモンの発育曲線です。「神経系」の発育は、一歳児から四歳児頃が急激に発育しています。人間の生きていく手段の基礎が伸びる時期です。「食べる」「歩く」「寝る」「話す」「聞く」「時間」「自己防衛」…ですね。
神経系の基礎が伸びていく年齢は、8から10歳で100%なんですね。
1歳児と5歳児の郵便ごっこ遊びを通じた交流です。真似遊びですが、「神経系」の発育盛んな時期なので、こんな簡単なことはできます。でも、保育教諭の温かい支援と言葉かけがあって、できることなんです。
保育室にいる1歳児の保育教諭の他、プレールームでも、もう一人の補助教諭が1歳児の保育に当たっています。
未満児の子どもには以上児と異なり、乳幼児一人一人のそばにいて、子どもたちに常に寄り添って、このように保育をしています。
ですから、給食を食べる時間は、午睡のために、保育室を暗くした中で、音をできるだけ立てないで、冷えたご飯とスープを食べなければならない時が多いです。調理室は、できるだけ冷めない給食を先生たちに食べてもらうように工夫を繰り返しています。子どもたちをみんな午睡させてから、順に給食を食べているのです。みんな一斉に午睡できるわけではありません。保育室を、子ども一人一人に応じた午睡場所を道具で仕切って、時間をずらしながら場所を変えているのです。
未満児の保育室に、たくさん「つい立て」のある理由は?何かわかりますか?以上児の先生、保護者の皆さん、考えてみてください。