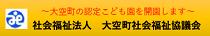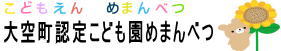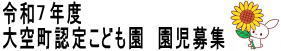令和6年度園だより第9号が発行されました
アーカイブ
園だよりR6【第8号】
令和6年度園だより第8号が発行されました
第2回園内研究会(10月17日)
今年度最後の園内研究会を行いました。
来賓に北海道教育庁オホーツク教育局教育支援課義務教育指導班指導主事の的場暁代さまをお迎えしました。
幼児期までに育ってほしい「10の姿」を意識した保育が重点項目です。教室にとどまらず,グランドでも園児たちの遊びがたくさんありました。
秋を意識した製作物がお部屋の前に展示されたり,グランドでは身体を使った粗大運動,自然と異年齢の交流が発生したり,各々が遊び込んでいました。
先生方の環境構成にもねらいがあり,子どもたちにこうなってほしいという思いが込められていました。
畑の収穫遊び,製作の楽しさや作物を収穫する喜びを疑似体験しています。 研究協議ではたくさんの付せんが貼られています。5つの領域,10の姿,研修の視点にそった
話し合いが熱心に行われました。
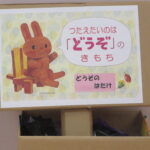



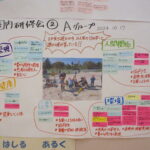


園だよりR6【第7号】
令和6年度園だより第7号が発行されました
第5回園内研修会~学びの芽を育む幼児教育~(9月4日)
今日の研修は,幼児教育と学校教育の連携や協働について文部科学省が制作した動画を観ました。
幼保小連携は,どこの研究会に出席しても幼児教育にとっても低学年の学校教育においても話題に上るようになってきました。
幼児教育は方向性を示す後ろ伸ばしの教育,積み重ねた経験(学びの芽)が小学校でさらに伸びていくことを期待しています。
就学を円滑に進めるために,幼児教育では*『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』を活用しています。
10の姿は5歳児までのゴールを想定し,自分ができるようになることを目指しています。
動画では,学びの芽を育む上で重要なこと,疑問や気づき,自分で考える,みんなで話し合う,失敗してもまた挑戦するなど
さまざまな経験を積み重ねることで問題を解決する力やコミュニケーションを図る力が育まれるとまとめています。
子どもたちが「やってみたい」という興味のエンジンがかかるようにどのような環境を構成するか,保育教諭の関わり方も重要なことを示唆しています。
*『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』子どもの育ちを保育者が「見取る」上での視点となるもの。
10の姿には,①健康な心と体 ②自立心 ③協同性 ④道徳性・規範意識の芽生え ⑤社会生活との関わり ⑥思考力の芽生え
⑦自然との関わり・生命尊重 ⑧数量や図形,標識や文字などへの関心・感覚 ⑨言葉による伝え合い ⑩豊かな感性と表現
があります。

園だよりR6【第6号】
園だより令和6年度【第6号】が発行されました
第2回園内委員会(7月23日)
第2回目の園内委員会を教育相談員の武田さん,大空町役場から山崎さん,女満別小から白戸さんに来園いただき開催しました。
最初に各クラスの気になるお子さんについて情報交流しました。少しずつ出来ることが増えてきています。
継続して支援が必要なお子さんもいます。発達支援センターや大空町役場福祉課,教育委員会など専門機関との一層進んだ調整や協議が必要なご家庭もあるように感じました。
今日のメインは保護者対応についてです。保育教諭は保護者にも適切な支援を行う必要があります。
保護者対応は異校種においても永遠のテーマであり,こども園でも同じような難しさを持っています。
信頼関係をどう構築していくか,先生方がどのような手立てで取り組んでいるか,その効果はどのくらいあるのか,振り返ってみることも必要です。
保護者さんへの伝え方を工夫したり,日々の活動が成長につながっていることを伝えていくことは大切です。
「こういうことをしたら,これができるようになった」と具体的な動きを示すことで保護者さんと共有できます。
本園ではドキュメンテーションで日常の子どもの姿や言葉を記録し,どのような学びや育ちがあったかを可視化しています。
また,1対1のやりとりには校務支援システムの連絡帳を使って個別に情報を共有しています。
ただし,連絡帳にはいくつか留意点があります。若い先生方は,その留意点については習得していない先生も多いはずです。
自ら自信をもち,保育のねらいや思いを効果的に発信できるようになることは資質向上には不可欠です。
今年度の研修は,先生方の悩みに寄り添うことをテーマにしています。保護者対応は組織的に取り組んでいく必要があります。
園内研修や園内委員会で資質向上を図っていきたいです。


園だよりR6【第5号】
園だより令和6年度【第5号】が発行されました
第1回園内研修会(7月18日)
管内こども園の保育教諭が集まり本園で研修会を行いました。
訓子府,ひがしもこと,滝上から8名の先生方にお越しいただきました。
午前中は,保育公開として園庭での水遊びや砂遊びを参観していただき,午後からは研究協議を行いました。
今年度は,研究主題を「遊びを通して,友達とつながり合う姿を求めて」と設定しました。
遊びを通して子どもたちがつながりを感じるための保育教諭の援助のあり方や環境構成の工夫を追究していこうと考えています。
研究協議①では,本日の保育について,そのねらい,評価の観点について振り返りを行いました。
一つの遊びから好きな遊びへひろがったり,異年齢の関り,自分のやりたいことをしっかり考えて参加する,楽しく遊ぶための工夫を考えていた等の反省が出ていました。
研究協議②では,3つのグループに分かれてワークショップ形式で協議を行いました。子どもの活動場面を「つながる」ことをテーマにいろいろな意見が出されました。
最後にまとめとして訓子府町認定こども園教務主査,北海道幼児教育相談員であられます矢口真美さんにご指導ご助言をいただきました。
①つなげるために道具を活用する。②発達段階に応じた遊びや学びを保障する。③ひとつの遊びから次の行動が生まれ,それがつながっていく。
④研修は大変だけど,あきらめが肝心,すべては子どものために等々,多岐にわたって示唆に富んだ助言でした。一つでも多く本園の研修に活かしていければと思います。
参加された他園の先生方にも貴重な意見をいただきました。ありがとうございました。







園だよりR6【第4号】
園だより令和6年度第4号が発行されました