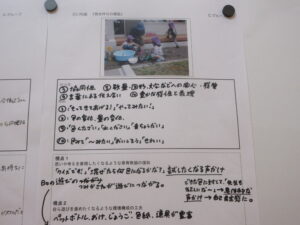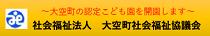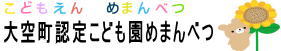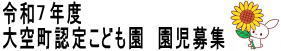園だより第11号が発行されました
アーカイブ
令和7年度園だより【第10号】
園だより第10号が発行されました
令和7年度園だより【第9号】
令和7年度園だより【第9号】が発行されました
令和7年度園だより【第8号】
令和7年度園だより【第8号】が発行されました
令和7年度園だより【第7号】
園だより【第7号】が発行されました。
第49回オホーツク管内認定こども園教育・保育研究大会(9月18日)
9月18日にオホーツク管内こども園教育・保育研究会主催(後援は社会福祉法人大空町社会福祉協議会)である研究大会が本園で行われました。
この研修会は以前にもご紹介しましたが,滝上・訓子府・大空町(女満別,東藻琴)の4園からなる組織で,毎年,保育教諭の専門性の向上を目的に開催されています。
来賓として佐呂間町教育委員会の元教育長(現在は公立学校共済組合本部総務部長)の谷川 敦氏,北海道教育庁オホーツク教育局教育支援課学校教育指導班指導主事である佐藤 亮太氏にお越しいただき
ました。
開会式では会長から,今後の幼児教育のあり方として「環境を通して行う教育」が求められること,幼児の主体性をどう育んでいくのか,環境と主体性が今後の幼児教育のキーワードになることが述べられ
ました。
午前中は未満児を含め以上児のクラスの保育公開,午後からは谷川氏の講演で『幼保小連携のあり方』~架け橋プログラムの作成~について,なぜ幼保小が必要なのか,佐呂間町の取組,幼保小の架け橋プ
ログラムのモデル地域での成果に係る調査結果などを紹介いただきました。
研究協議ではドキュメンテーションをテーマに各グループで協議を行いました。小グループであったことから話し合いがどのグループでも熱心に行われていました。
最後に,佐藤指導主事からは,規範性の高さ,ドキュメンテーション,10の姿を踏まえた「こども理解」について,今後の保育指導において示唆に富んだ助言をいただきました。
令和7年度園だより【第6号】
園だより【第6号】が発行されました。
令和7年度園だより【第5号】
園だより【第5号】が発行されました。
令和7年度園だより【第4号】
園だより【第4号】が発行されました。
第1回園内研修会(6月11日)
昨日,本園で第1回園内研修会を行いました。
助言者としてオホーツク教育局教育支援課学校教育指導班指導主事である佐藤 亮太氏と北海道幼児教育相談員の硯見 直美氏を招いて普段の保育指導を参観いただきました。
他にも研究会の三つのこども園から保育教諭も来園し,その専門性の向上を図りました。
本園の研修主題は「思いや考えを表現し,遊びに向かうこども」の育成です。保育公開をしたのは3歳,4歳,5歳児ですが,保育教諭の支援のあり方や環境の構成について協議を進めていきました。
研究協議では今日の保育指導の各場面をピックアップした写真をもとに,10の姿のどの部分が育まれているのか,その理由を含めてグループでそれぞれ話し合いを行いました。
最後に硯見氏からは「主体性」を育む保育指導について,佐藤氏からは今日の成果と課題について助言をいただきました。